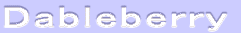5日。
たった5日。
だからそのあいだだけ、もっとその顔を見せて。
思い浮かべば、思慕の溜息が出るほど、もっと。
「美味いよ、ほんと」
その言葉に、ほっと息をついた。
彼のためにわざわざホークアイに教えを請うたのだ。1週間分の仕事を3日で完遂することを約束してまで。
彼好みの茶葉、ミルクの種類、茶の抽出時間、サーブする時の温度。
聞いたときはまさか彼女がそんな細かいところまで、彼好みのお茶を煎れているとは思わなかったが―――もっとも、だからこそ彼女が煎れるお茶は彼の絶賛を浴びているのだが―――それこそ微にいり細にいり、ビシビシとご教授された。
途中で挫折しそうになる私を励ましてくれたのは、ひとえに彼女の『おいしいお茶を煎れてあげると、ちょっと照れた顔で本当に嬉しそうにしてくれるんですよ?』という言葉だった。
今まで彼女にしか向けられなかった笑顔が、もしかしたら自分にも向けられるようになるかもしれないのだ。頑張るしかないだろう。
そうして練習した甲斐あって、本日2度目のお茶にも笑顔を浮かべてくれた。
その笑顔が1度目よりややぎこちないのは、残念な気もするが致し方ないことだ。
彼は、今、私の告げたとおり、私の家にいるのだから。
本日中に済まさねばならない仕事を終わらせて、街へ出た。
いつもこうやって早く仕事を終わらせてくれればいいものをと、呆れた視線を送ってくる中尉に感謝する。唯一私の事情を知る彼女の協力がなければ、こんなに余裕をもって明るい時間の街に出ることもなかった。
もうすぐヴァレンタイン・デーがくる。
年月を経るごとに成長しているはずの子供は、しかし私の求めるほうの情緒面で成長しているとは言いがたく……いや、ゆっくりとではあるが成長の度合いを見せてはいた。
視線をはずしているときに感じる熱や、時折見せるどこか安心しているような、甘えたような仕草は、確かに成長の証とも言えるだろう。本人はきっと意識していないだろうが、それは時に私を惑わすに十分なものだ。
けれど私が望むところまで追いつくには、まだしばらくの時間が必要であるように見えた。
明日にも報告書を携えたエドワードがここに来る予定だが、そんなエドワードが世間のイベントに便乗してくるはずもない。今年も真に欲しいものを思いつつ、あの甘ったるい匂いに一日中悩まされなくてはならないのかと思えば、それだけで気が滅入る。
それなら私が用意すればいいのだろうが、前述のようにいまだ時期尚早に思えた。一気に距離を詰めるのはいいが、それをかわされてしまうと、きっと私のほうがどうしたらいいのかわからなくなるだろう。
だからせめて、国家錬金術師の義務を果たしにくる彼に、好みの本と、好みのお茶を。甘い物が好きなのに食物を摂取できない弟―――当人は気にしていないどころか、疲れをとるために兄に勧めたいくらいらしいが―――のために、旅の最中は極力控えているらしい、好物の菓子を。チョコレートを使ったものであれば、少しは私の願望も満たされるだろう。
そうして茶葉を買い、菓子を買い、司令部に戻る私の視界のすみに、何かがひっかかった。
「いい石ですよ、ダンナ」
思わず立ち止まった私に、商品に興味を持ったと思った露店の店主が声をかけてきた。
誰がダンナだと思いつつ、露店の店主がある種有名な男だということに思い当たった。
法に抵触するギリギリのところで商売をする男。言い換えれば、マズイところをうまくかわして、オイシイところだけを頂戴している、鼻の効く男(もしかして、あまり歓迎したくはないが、はたから見れば私もこの部類に入るのではなかろうか)。どこから探し出したのかと聞きたくなるような古物から、少なくとも軍服を着ているあいだは知ることができなさそうな情報まで。ギリギリのものを売るからには、出所は言えずとも正確なものを。確かハボックが何度かこの店主から情報を買っていたはずだ。この男なら、私がどこの誰であるかもよく知っているだろう。
少し欠けた前歯を口の端に覗かせた、商人の胡散臭さとは裏腹に、思わず近寄った私の目にも、くだんの石が良いものだと知れた。
柔らかな布に大切に包まれた石はほんの小粒だが、色は濃く……そう、彼の捜し求める石はこんな色ではないかと思わせる深い紅。そのくせ透明度は高く、素人目にもカットは上々。
彼の身に纏うコートの色に似ているからか、捜し求める石に似ているからか。もちろん賢者の石とは本の記述を信用するとしても、こんな露店で売っているようなものではないのだが、その紅さに魅かれた。
「黄金の方にはよく似合うでしょうねえ」
「彼女に贈るつもりは、ないよ」
もみ手をするように話しかけてきた彼を、私は遮ったつもりだった。
君が言っている相手―――この場合、ホークアイだが―――に贈るつもりは毛頭ない、と。
「紅のコートを着ていても、着てなくても……ああそうだ、耳なんかに映えそうじゃないですか」
よけりゃあ、金具の細工もしますよ?
さらにかけられた言葉に、正直、不覚なこと甚だしいが、私の心臓は止まりかけた。
一体、いつ見ていたのか。
そしてなぜ気付いたのか。
こうなれば司令部までひっぱって追求したいところではあるが、きっとこの店主は素直に吐かないだろう。
彼の損得を考えると金がからまない限り、そう容易く他に吹聴しないだろうということもわかっているが、こうなれば私のとるべき行動はただひとつ。なにより私はこの石が気に入った。店主が言うとおり、金の髪の隙間から垣間見える紅は、私を震わせてくれるに違いないのだし。
「現金がいいか?」
「へえ、毎度。細工は必要ですかい?」
「そうだな。どれくらいかかる?」
「そうですねえ、台座にいい細工をしたいなら5日は見てもらいたいですねえ」
当然、彼の身につけるものなら細工のいいものを選びたい。
私は躊躇うことなく頷いた。
「細工はあまり華美にならず、品のいいものにしてもらいたい。ところで、今日は裸石のまま持って帰りたいんだが」
「へ? その分細工する時間が遅くなりますがね?」
「構わんよ。そのままの状態でも色合いを確かめることはできるだろう?」
裸石でも彼の肌に合わせることはできる。
完成するまで秘密にするのもいいが、そのあいだに旅に出られても困るし、なにより私が見てみたかった。
「どうぞご自由に。それじゃ早めに石を持ってきてくださいよ、マスタング大佐」
口止め料も兼ねているのか、価格はやはりそれなりに高額だったが、即金で支払った。すぐに現金を手にすることができた店主は嬉しげに笑って、ご丁寧にもケースに入れて石を寄越した。
最後の呼びかけに、やはり食えない相手だと苦笑しつつ、私は露店を後にした。
彼が私の贈り物を受け取るならば、余人計り知れぬ絆で結ばれた弟くんには申し訳ないが、その贈り物が完成するその時まで、彼を独占させてもらうと決めた。
こうして贈り物を用意した以上、引っ込みがつかなくなったと言いたければそう言ってもいい。机の引き出しの奥に眠らせたままでいるつもりはない。
ただ、彼をこうして待たざるを得ない立場であっても、気持ちまで悠長に待たなくてもいなくていいということを思い出しただけだ。
そして念願叶って、彼はここにいる。
「そう俯かないでくれると嬉しいのだが。顔が見えないのは……困るね」
羞恥か混乱か、おそらくその両方のせいだろう、司令部から逃げ出そうとしたエドワードを捕らえて食事に行き、帰りは宣言通り私の家に連れてきた。今、大人しく私の差し出すお茶を飲んでいるのは……どちらかと言えば羞恥か。目が合うたびに恥じらい顔を伏せる様子は、何度見ても愛らしいものだが、こう視線を合わせてくれないのも哀しいものだ。
まあ、原因は多分に私にある。
それを解いていくのも、こうなれば私だけの楽しみだろう。
その口に、私の名を呼ばせるのも。
「顔をあげてくれないか、エディ?」
君と過ごす大切な5日なんだから。
もっと顔を見せて。
もっと声を聞かせて。
もっと、君を見せて。
君が私を忘れられなくなるほどに。